参加登録結果
参加形態別
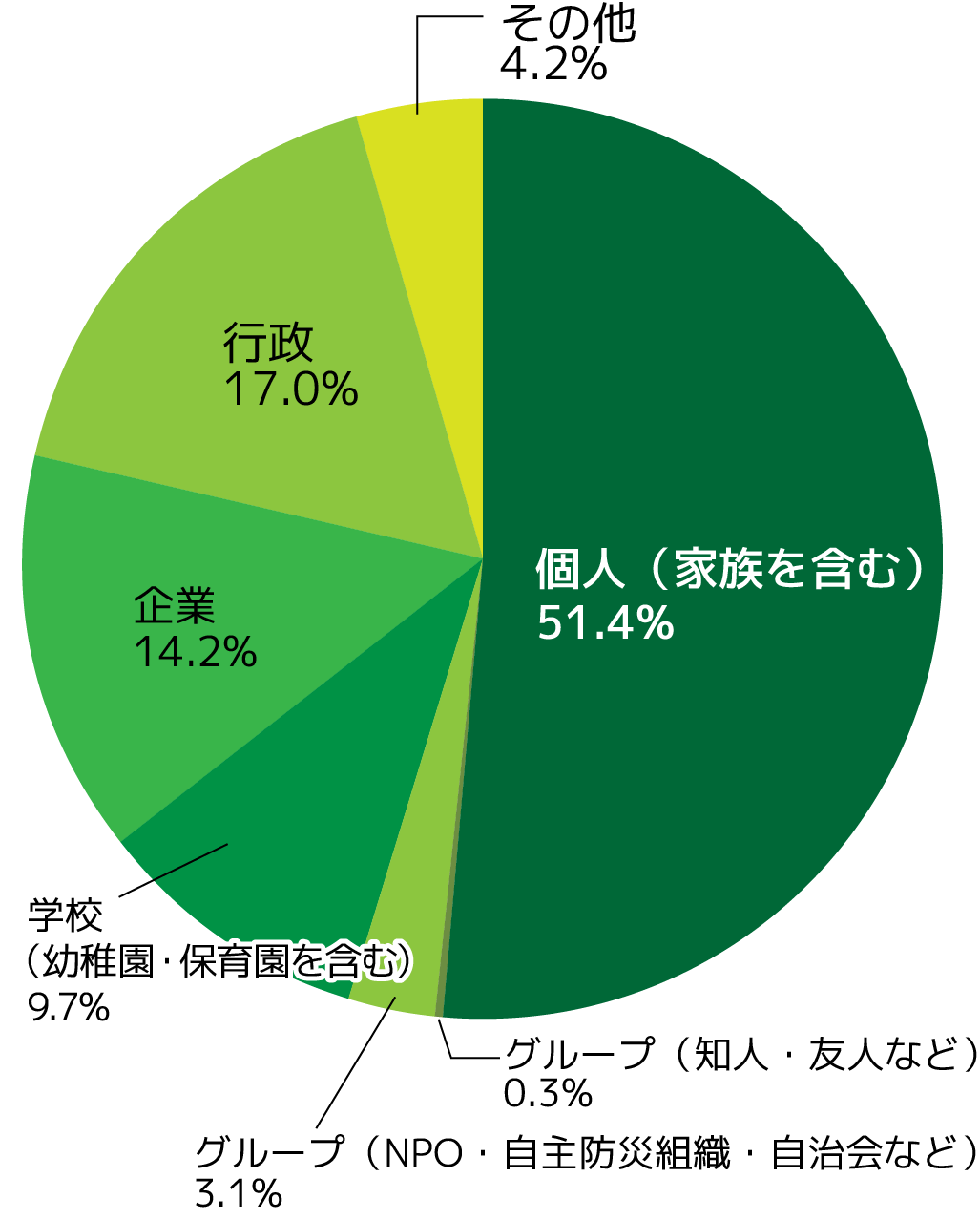
| 参加形態 | 登録数 | 参加人数(人) |
|---|---|---|
| 個人(家族を含む) | 148 | 272 |
| グループ(知人・友人など) | 1 | 3 |
| グループ(NPO・自主防災組織・自治会など) | 9 | 171 |
| 学校(幼稚園・保育園を含む) | 28 | 3,422 |
| 企業 | 41 | 1,203 |
| 行政 | 49 | 3,223 |
| その他 | 12 | 2,299 |
| 合計 | 288 | 10,593 |
参加登録者からのメッセージ
参加予定日
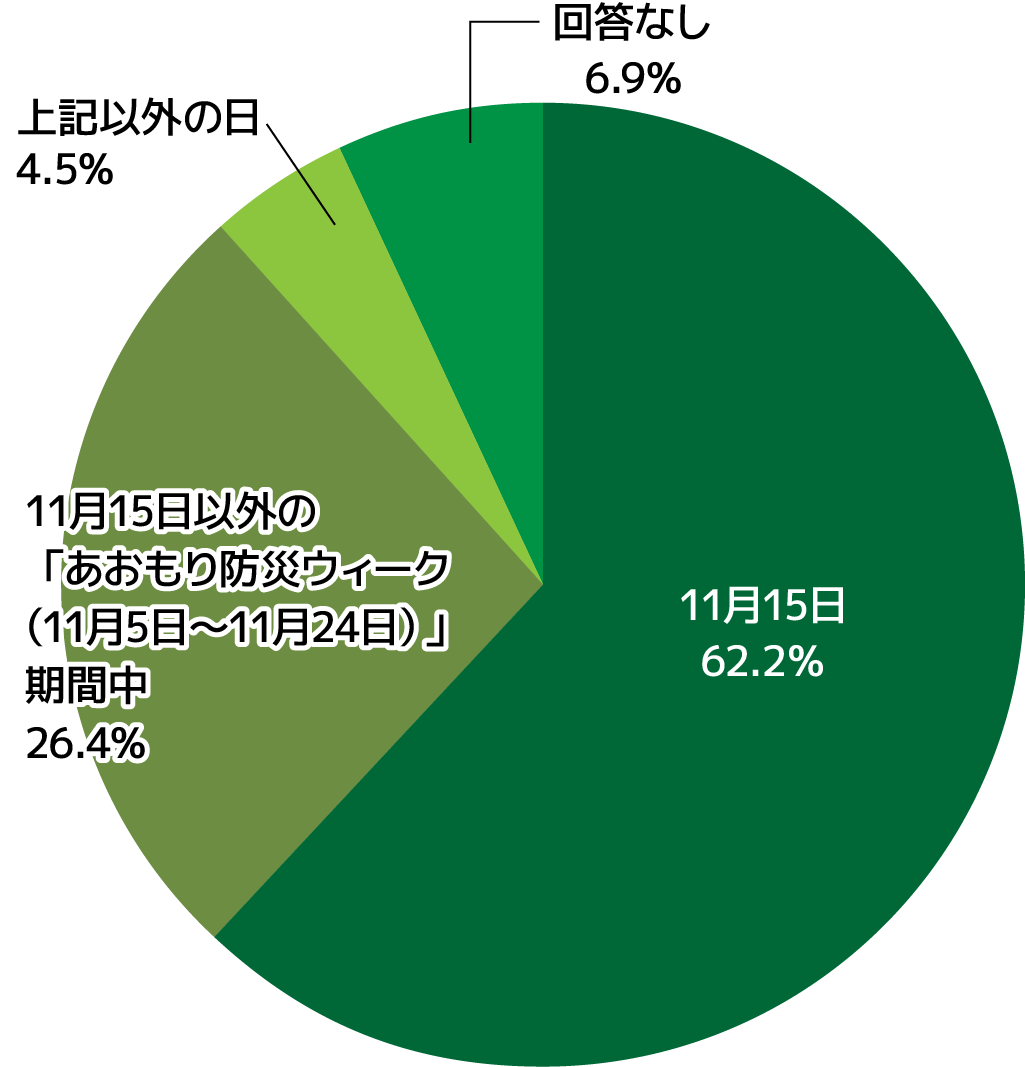
| 参加予定日 | 登録数 | 参加人数(人) |
|---|---|---|
| 11月15日 | 179 | 9,232 |
| 11月15日以外の「あおもり防災ウィーク (11月5日~11月24日)」期間中 |
76 | 1,061 |
| 上記以外の日 | 13 | 250 |
| 回答なし | 20 | 50 |
| 合計 | 288 | 10,593 |
実施アンケート結果
「チャレンジ宣言」の情報を知った手段
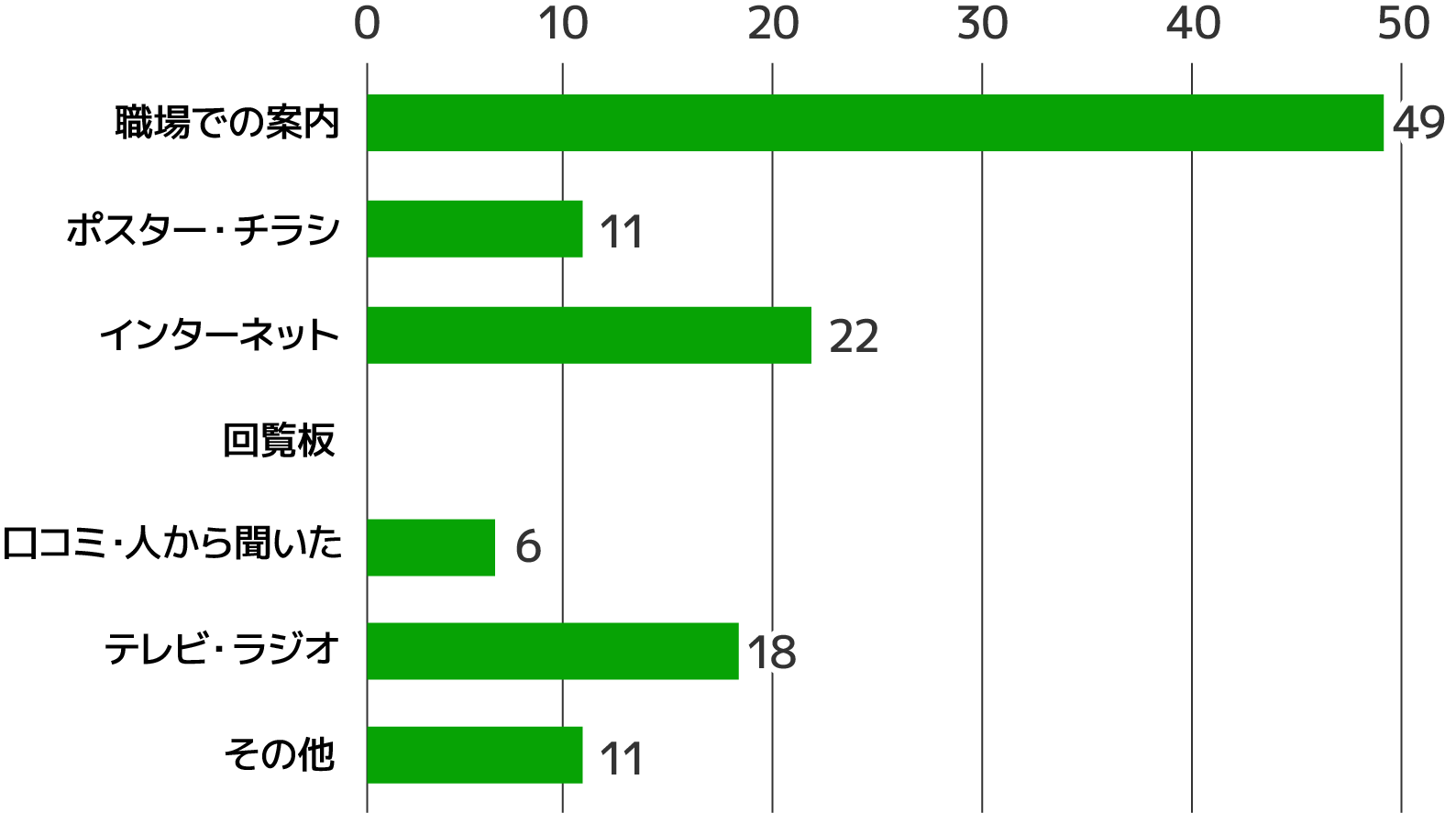
【その他】
- 市町村からのメール・LINE等
- 新聞広告
取り組んだ「チャレンジ宣言」の内容
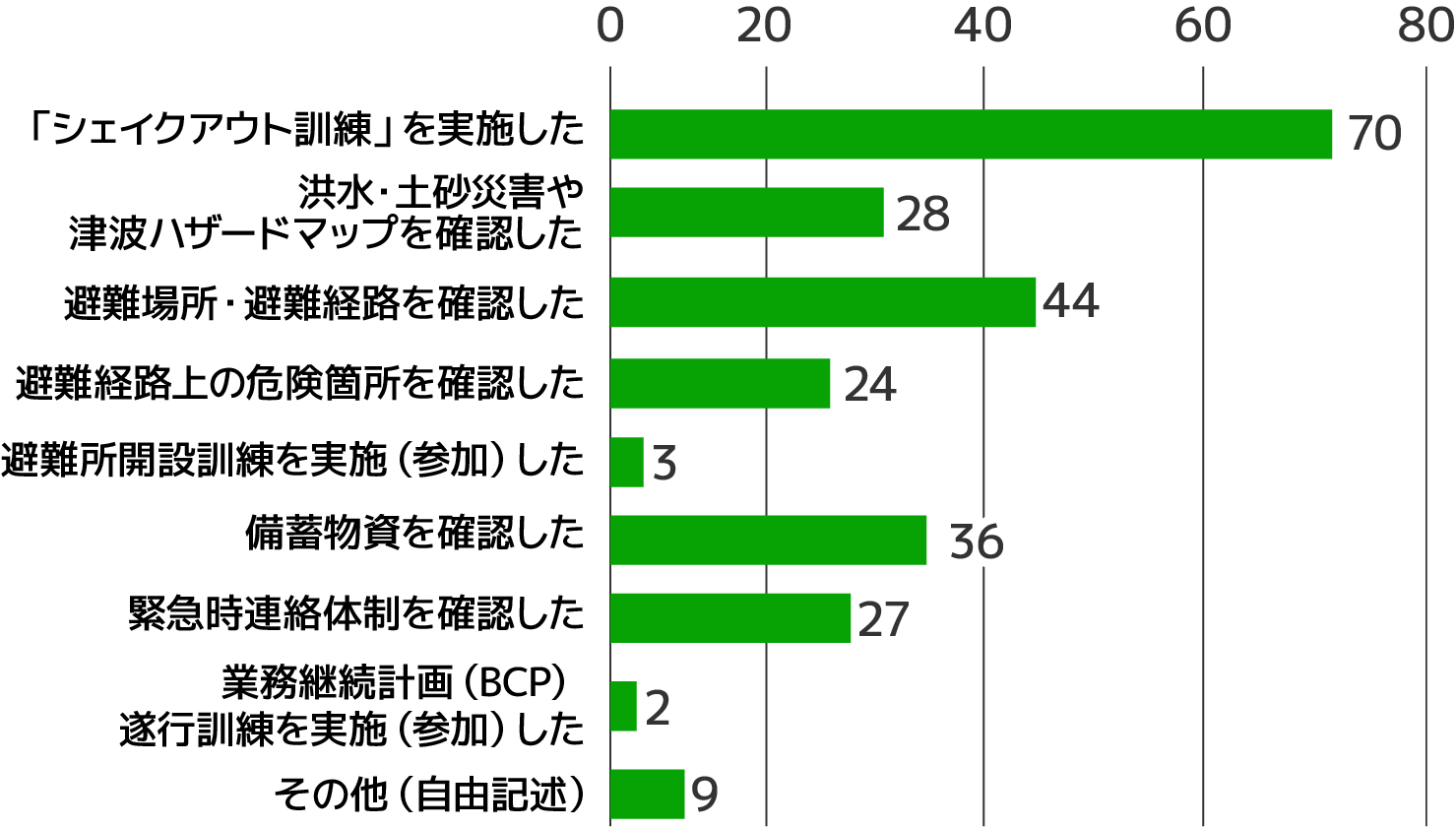
【行政機関・公的機関】
- 火災発生の模擬通報、消火器を使用した消火訓練
- 災害発生時の初動対応の確認
【自主防災組織】
- 防災研修会の開催
- ①防災資機材の作動確認、通信及び照明用具等の電池交換②防災備蓄品の新規購入品目の決定
【その他団体】
- 避難する際の携行品リスト作成
【個人・家族】
- 防災ポーチの作成
